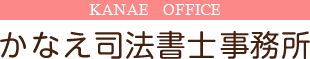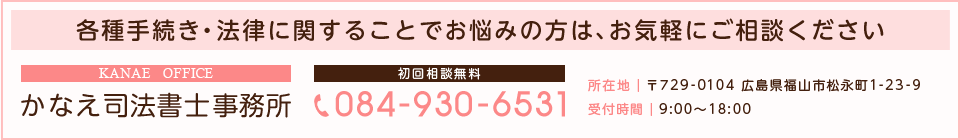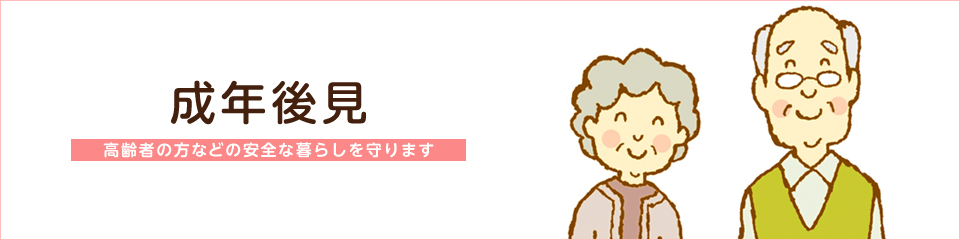
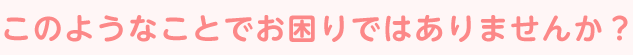
このようなことでお困りではありませんか?
- 子供も他に頼れる親族もいない。今後の生活が心配…
- 最近、訪問販売で高額な必要のない商品を買ってしまう
- 認知症の親名義の預金払戻しを受けようとしたところ、金融機関から後見の手続きを勧められた
- 相続の手続きをしたいが、親が認知症で協議ができない
- 自分が先立った後、知的障がいをもつ子供の将来が心配
- 後見の手続きについて相談したい
成年後見制度で安全な暮らしをサポートいたします
体力や判断力が衰えると、自分だけでは物事に対処できない状態になってしまうこともあります。
そのような将来に不安や心配を抱くご本人様やご家族、また、判断能力が不十分な状態にある人の権利を守る仕組みが成年後見制度です。
かなえ司法書士事務所では、成年後見制度により高齢期にある方や、そのご家族を支えていくための支援サービスをご提供いたします。お気軽にご相談ください。
成年後見制度開始までの流れ
1 事前予約

お電話(084-930-6531)にてご予約ください。ご予約の際に、相談内容について簡単にお聞かせください。
2 ご相談

適切な解決方法をご提案させていただきます。また、手続きに必要な書類もお伝えします。
3 裁判所への申し立て

裁判所へ申立書などの書類を提出します。
4 後見人等の選任

裁判所は後見人等の選任の必要性について調査し、必要があると認めた場合、選任します。
5 後見事務の開始

裁判所監督のもと、後見人等は被後見人等の事務を行います。
成年後見に関するよくあるご質問
-
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は、財産管理や契約などの法律行為を本人に代わって行います。
ただし、身の回りの世話や日用品の買い物、介護などは一般的に成年後見人の職務ではありません。
なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。